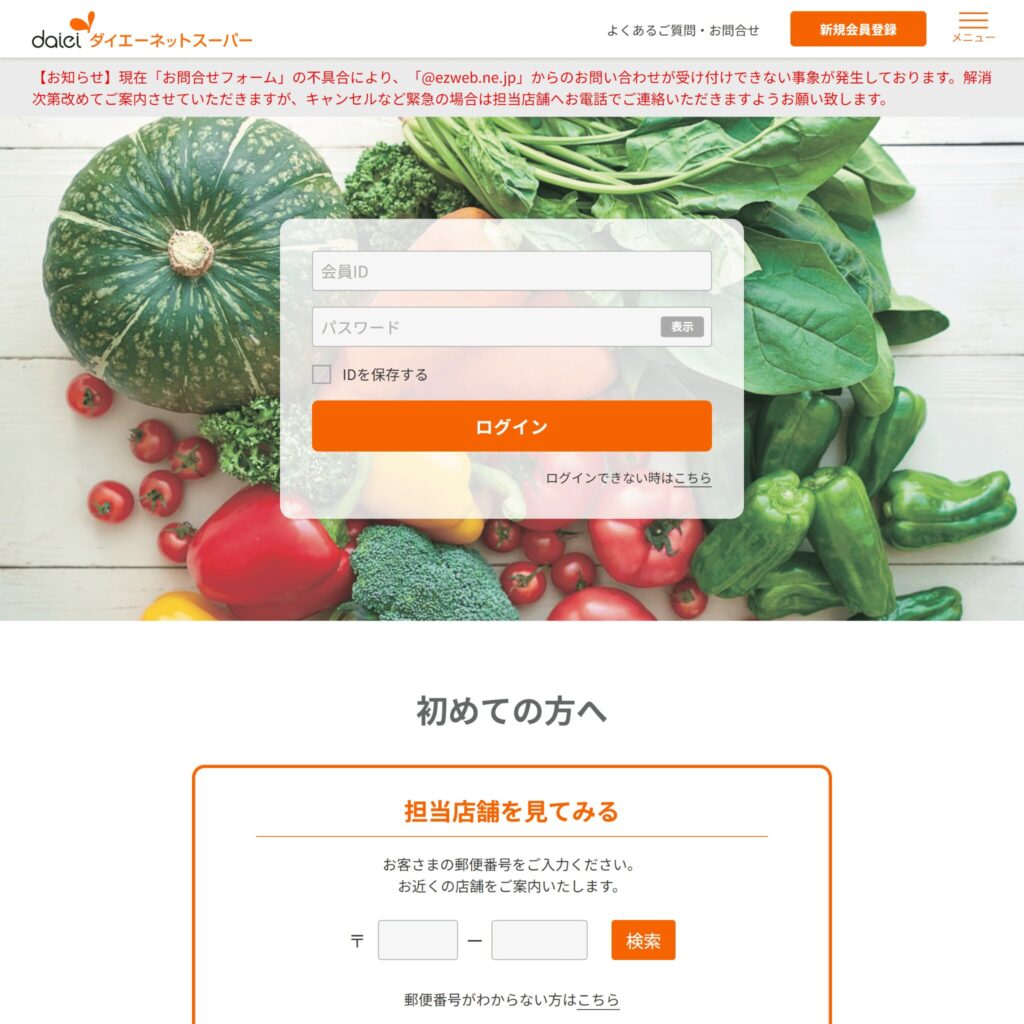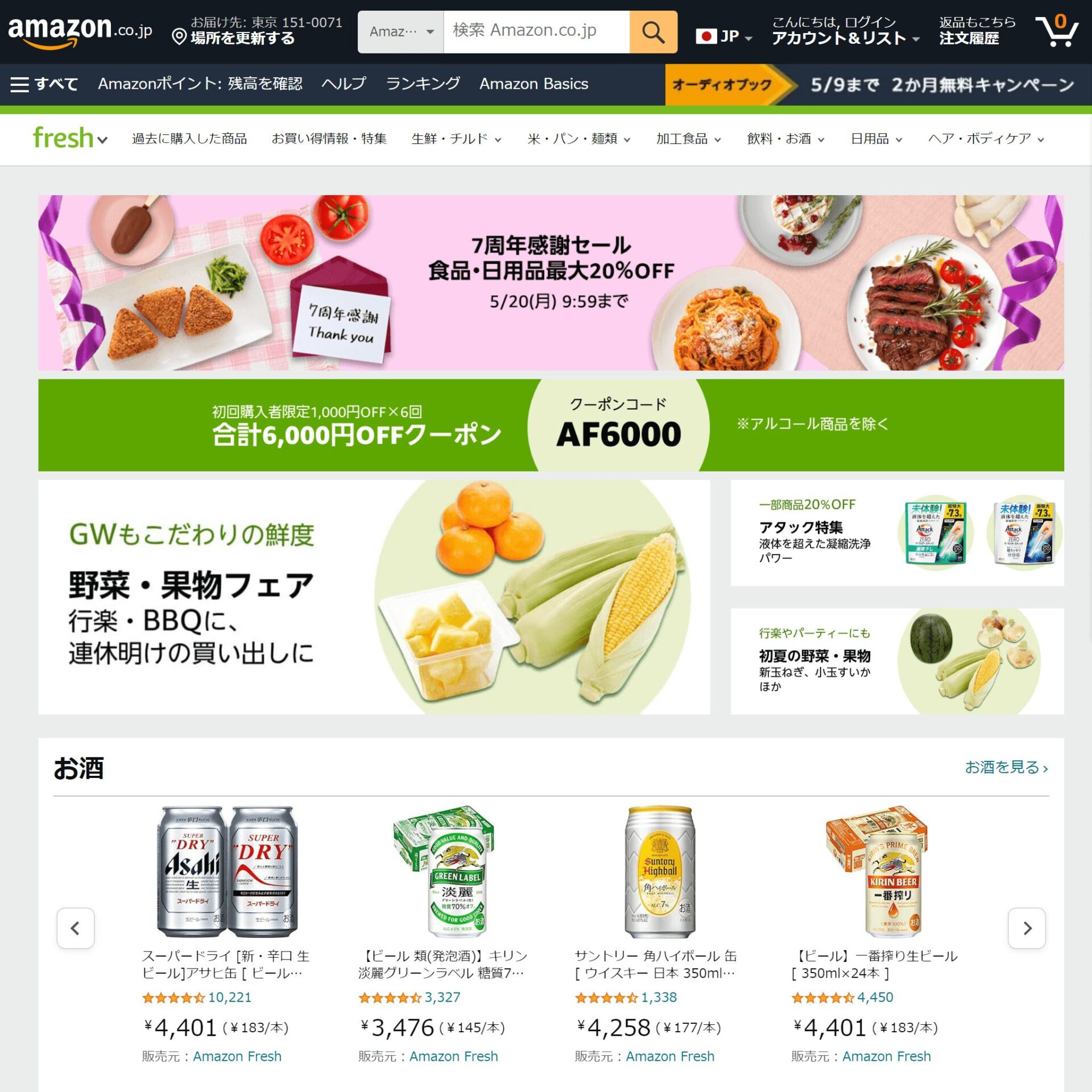近年ニュースなどで「買い物難民」というワードが取り上げられることが増えています。買い物難民とは、少子高齢化や地域過疎化により、買い物が難しくなっている人たちのことです。そこで本記事では、買い物難民の定義や発生する原因、問題の解決方法などをまとめて解説します。ぜひご一読ください。
買い物難民の定義
「買い物難民」とは、過疎化や交通機関の廃止、食料品店の減少などにより、日常の食料品や生活必需品の購入が困難な人々を指す言葉です。2010年前後から書籍や農林水産省の調査をきっかけに「買い物弱者」「買い物困難者」といった言葉が注目され、メディアでも取り上げられるようになりました。
これらの言葉に明確な統一定義はなく、各省庁によって定義は異なります。農林水産省の定義は「高齢者等を中心に、食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる人」、経済産業省の定義は「流通機能や交通網の弱体化とともに、日常の買物が困難な人々」です。
また、農林水産政策研究所による具体的な定義では「店舗まで500m以上かつ自動車利用が困難な65歳以上の高齢者」が買い物難民(食料品アクセス困難人口)とされています。食品アクセス問題について農林水産省が2024年に実施したアンケート調査によれば、質問に回答した1083市町村のうち、89.7%にあたる971市町村が「買い物難民の対策が必要」としているのです。
また、この問題は神奈川県全域にも広がりつつあります。都市部は人口が多く、必要な情報の把握も難しいため、買い物難民への支援が遅れる傾向にあります。今後は官民が連携して、買い物難民の所在やニーズを的確に把握し、地域ごとの特性に応じた支援やサービスを提供することが求められています。
買い物難民が発生する原因
買い物難民が発生する主な原因は、大きく3つに分けられます。
高齢者の増加
まず第一の原因は「高齢者の増加」です。2020年8月時点で日本の高齢化率は28.7%に達し、今後も上昇が見込まれています。とくに75歳以上の人口増加が著しく、2005年から2015年の10年間で買い物難民の割合は65歳以上で21.6%増、75歳以上では42.1%増加しているのです。
高齢者は体力的に移動が困難なだけでなく、改正道路交通法の影響で運転免許の返納が推奨されており、自家用車を使えない人が増えています。そのため、地域や家族の支援がなければ日常の買い物すら困難になるケースが多く、買い物難民化しやすいのです。
食料品販売事業所の減少
第二の原因は「食料品販売事業所の減少」です。郊外型の大型スーパーとの競争により、小規模な八百屋、魚屋、肉屋などの専門店が減少しています。これらの店舗は地域住民、とりわけ高齢者にとって貴重な買い物先でした。
一方で、大型スーパーも採算が合わなければ撤退してしまうため、突然買い物手段を失う地域が出てくるのです。
支援の遅れ
第三の原因は「支援の遅れ」です。農林水産省の調査によると、買い物支援の必要性を認識している自治体は全国で85%にのぼりますが、実際に対策を講じている自治体は68.6%にとどまっています。とくに大都市では66.7%と全国平均より低く、人口が多く個々の状況を把握しにくいため、支援の手が届きにくいという問題もあります。
早急な対応が求められる中、支援体制の整備が追いつかない現状が、買い物難民を増加させている一因となっているのです。
買い物難民には「ネットスーパー」の活用がおすすめ
買い物難民の解決策の1つとして「ネットスーパー」があります。ネットスーパーは、実店舗ではなく、インターネット上で食料品や生活必需品を購入できるサービスです。
ネットスーパーを活用するメリット
買い物難民になりやすい高齢者にとって、ネットスーパーはさまざまなメリットがあります。まず何より、近隣にスーパーがない場合でも、注文すれば郵送で届けてくれる点です。
これにより、食料品の調達がグッと楽になることでしょう。また、買い物に出かける必要がないため、腰や膝が悪い人でも負担なく買い物が可能です。
ネットスーパーを活用するうえでの課題
高齢者の人の中には「ネット環境がそもそもない」「インターネットが苦手」といった課題を抱えている人も多いです。また「インターネットで買い物をしたことがないので不安」という人もいることでしょう。
そういった場合は、家族や福祉関係者のサポートが必要です。他の人の力を借りることで徐々にインターネットに対する苦手意識を払拭し、最終的には自分だけで買い物を行えるようになるのがのぞましいです。焦らず、一つ一つ積み重ねていくことが重要といえます。
まとめ
買い物難民とは、少子高齢化や地域の過疎化、交通手段や食料品店の減少により日常の買い物が困難になっている人々のことを指します。とくに高齢者の増加に伴い、移動手段を持たない人が増え、都市部や地方を問わず深刻な問題となっています。また、地域に根ざした小規模店舗の閉店や支援体制の遅れも事態を悪化させています。こうした中、解決策の一つとして注目されているのが「ネットスーパー」の活用です。自宅にいながら食料品や日用品を注文できるため、買い物が困難な人々にとって心強い選択肢となります。ただし、ネット環境の整備やITリテラシーの支援といった課題も残っており、家族や地域、福祉との連携が不可欠です。今後は、官民一体となった支援が求められます。